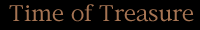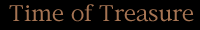|
2nd January, 2008
|
長椅子を覗き込みながらアランが言った。
「眠っちゃった?」
「みたいだ」
ゴードンは傍らのテーブルにあったワインのボトルとグラスを脇によけながら答えた。
寝椅子ではジョンが気持ち良さそうに眠っている。
夜遅く、テラスで一人で星を眺めていた彼にワインを奨めたのはゴードンだ。
そして、昔話に花が咲いているうちに、いつしかジョンは眠ってしまった。
ジョンに上掛けをかけてやりながら、ゴードンはその無防備な寝顔にクスッと笑った。
あの時と反対だ…。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
その夏のシーズン、ゴードンは周囲の期待どおりジュニアの各大会を総誉めにしていった。
だか、シーズン終盤にペースが崩れた。
今までは泳ぐたびにライバル達をしのいできた。
それがシーズン後半の数レースはトップに立てなかったばかりか、自己記録にすら届かない。
釈然としない自分の気持ちと周囲とのギャップに苛立った結果は、
無茶な泳ぎ込みによる故障と二週間の陸上トレーニング命令だった。
その日も、ジムでのトレーニングを終えて帰宅したゴードンは
すっきりしない気持ちで玄関をくぐった。
扉の脇のサイドボードに今日、配達された手紙が乗せられている。
ここに整理されているのは、もうお手伝いのラモーナが帰った証拠だ。
ほとんどはジェフ宛てのダイレクトメールだった。
他はジョンに一通 アランとジェフの連名が一通…、あった、自分宛だ。
コーチが何だかいっていた全米水泳協会からの審査書類だ。
ゴードンがため息混じりに封筒をカバンに押し込んだとき、ダイニングから話し声が聞こえてきた。
3年前にスコットがエール大学に進学し、
この9月にバージルがデンバースクールで学ぶために家を離れた。
ジェフは一昨日から、支社の急なトラブルで呼び出されて家を空けている。
ダイニングを覗くまでもない。声の主はジョンとアランだ。
ゴードンがダイニングを素通りして自室に行こうとしたとき、ジョンの声がした。
「ゴードン」
ゴードンは小さくため息をついてダイニングの戸口に寄り掛かった。
「なにか…」
アランがジョンと見ていたチラシから顔を上げた。
「おかえり。ゴードンはピザ、どれがいい?」
そのあっけらかんとした物言いに、ゴードンの眉間に思わず皺が寄る。
「ただいま。…なに?」
「ピザだよ。どれがいい?デザートも頼んでいいって、ジョンが」
さらに眉根を寄せたゴードンを見て、ジョンが席を立って歩いてきた。
「父さんもいないことだし、たまにはいいと思ってね」
「晩ご飯はラモーナが用意してるんじゃないの?」
「アランは明日の朝食当番を免れてご機嫌だよ」
キッチンの方を見たゴードンにジョンはウインクすると、小声でささやいた。
「とうとうセシルに引導を渡されたらしい」
「…へ?」
「アランだよ。ここ一ヵ月ほど様子が変だったんだ。昨日ひどく落ち込んでたから聞いてみたら…ね」
ちらりとアランの方に目をやると、ジョンはポンッとゴードンの肩を叩いて振り返った。
「決まったか?アラン」
「デザートはスペシャルサンデーがいいな。ペイパービュー見ながら。いい?」
「いいよ。好きなのを選んで予約しとけ」
そう答えながらジョンはゴードンに小さく口真似した。『少しは上向きだ』
歩み寄るジョンにアランがチラシを指差しながらはしゃいでいる。
その光景を、ゴードンは複雑な思いで眺めた。
セシルはアランの五年生の時からのガールフレンドだ。
二人は去年の九月に一緒にミドルスクールに上がって、そして…そのままだと思っていた…。
「ゴードン」
ジョンの声にゴードンは目をしばたかせた。
「どれでもいいなら、僕が決めちゃうよ!えーと…」
アランがチラシに顔を近付ける。アランのお気に入りのハワイアンを押しつけられたらたまらない。
「ペパロニとアンチョビのダブル。あと、ダイエット・コークのL。荷物、置いてくる」
慌ててそれだけ言うと、ゴードンは自室に向かって走っていった。
―――――――――――――――
リビングの大型テレビの前でピザの箱を開けた三人は半ばソファーに寝そべりながら、
ジェフが見たら間違いなく一言では済まないような夕食を取った。
アランの選んだペイパービューは今はやりのコメディアンが主演のスラップスティックで、
スクリーンの中では主人公が牛に追われながら公道を疾走している。
その光景にアランがピザを飛ばして大笑いをしていたとき、電話が鳴った。
「こっちで取らないでよ」間髪入れずにアランが言う。
画像をテレビに割り込ませるなという意味だ。
半ば呆れるゴードンの隣で、ジョンが音声だけにして端末を手に取った。
「…やあ、スコット」ゴードンの隣でしばらくスコットと話していたジョンは、
やがて映像通話に切り替えるために親機のもとに席を立った。
…なんだ、スコットか。何の用だろう…。
漠然と思いながらゴードンはスクリーンを眺めた。
隣ではアランがゲラゲラと笑っている。
最初はアランの騒々しさや映画の馬鹿馬鹿しさが気に障ったが、
いつのまにかゴードンはこの雰囲気になじんでいた。
よく、アランと二人でアニメを見ながらソファーで跳ねては父さんに怒られたっけ…。
そのときのジェフの顔を思い出して微かに顔をしかめながら、ゴードンはふと妙な懐かしさを覚えた。
以前は当たり前のことだったはずだ…、いつから忘れていたんだろう…。
電話を終えてジョンが戻ってきた。
「スコット、何だって?」
「ご機嫌伺いだよ。みんな元気かって」
横に座るジョンをゴードンはちらりと見た。
「で、なんて答えた?」
「アランはコメディ映画に爆笑して、君はこの環境にむっつりしてるって」
ジョンが思わせ振りにアランに目をやる。
ゴードンは指についたソースを舐めながらクスッと笑った。
いつしかスクリーンではエンドクレジットが流れ始めていた。
その向こうでカジノで大儲けをした主人公が100ドル札を振りまきながら車で走り去っていく。
それを見ていたアランの顔から、今までの笑顔がすうっと消えた。
「いいよな、映画は何でもうまくいって」
「そりゃ、作り話だからな。でも、主人公もそれなりに努力してたじゃないか」
コーラをすすりながら横目で見るゴードンに、アランは憤慨して答えた。
「筋書きの上でだろ。最後のポーカーなんて全部、運なんだから、絶対、現実にありっこないよ」
「運だけで勝てるわけないだろ、ギャンブルが。駆け引きとかテクニックとか…」
「じゃ、どんなテクニックなんだよ、言ってみろよ」
「教えてやろうか?」
唐突に声がした。
ヒートアップしていた二人が思わず振り向くと、
ジョンはカップの底のアイスクリームをスプーンで集めながら言った。
「ポーカーに勝つ方法」
「どうせお子さま向けバージョンってやつだろ」
ご機嫌斜めのアランが膨れっ面でそっぽを向く。
ジョンはそんなアランをちらりと見た。
「ラスベガスでも通用するテキサス・ホールデムを教えてやるよ。ただし…」
スプーンを一舐めすると、ジョンはカップをテーブルに置いた。
「誰にも言うなよ。ホーム・ゲームがばれたら懲役だ」
トランプを取りに立つジョンの後ろで、ゴードンとアランは無言で顔を見合わせた。
|
|
整理しきれなかった駄文が後半へつづく… -_-; → Go !
|
|